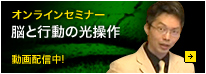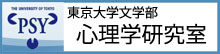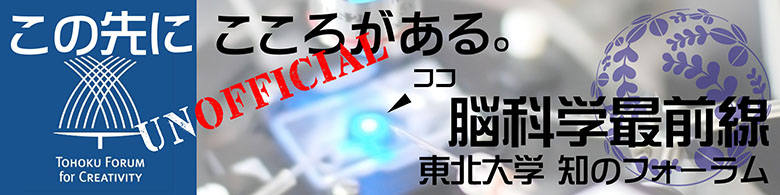東北大学・大学院生命科学研究科/超回路脳機能分野
兼・東北大学・大学院医学系研究科/超回路脳機能分野
メンバーページ
田島 大智

氏名:田島 大智(たじま だいち, Daichi Tajima)
現職:修士課程1年(生命)
所属:東北大学大学院生命科学研究科
超回路脳機能分野(松井広研究室)
専門:遺伝学、脳内エネルギー、学習と記憶
所在:片平キャンパス
学歴:
2025年3月 東北大学理学部生物学科 卒業発生ダイナミクス分野(指導教官:杉本亜砂子)
学士(理学)取得
2025年4月 東北大学大学院生命科学研究科
修士課程入学
超回路脳機能分野(指導教官:松井広)
一言:
私の主な関心は、記憶などの認知能力を実現するために脳の複数の細胞がどのように協調しているかということです。一般的にこれらの機能はニューロンによって実現されると考えられていましたが、実際には近傍のグリア細胞や血管もシナプスへの介入や栄養補給を通して大きな影響を及ぼしていることが判明してきています。このように脳という器官を包括的に研究することで、我々の認知能力に関する一歩進んだ知見が得られる可能性があります。知的なスキルが幸福度に直結する情報社会において、今まで根性論や「才能」という神秘主義などの文脈で語られることの多かった記憶や思考などの認知能力を生物学的に解明していく意義は非常に大きいと考えています。
私は、学部時代に東北大学理学部生物学科・杉本教授研究室で線虫の染色体構造の機能解明などを目的とした染色体操作技術について研究をしていました。この研究を通して得た遺伝子や細胞についての基礎知識などを、今後の脳の研究にも役立てていきたいと考えています。線虫は多様な進化によって様々な環境に適応しています。時には、最近縁種である2種が似ても似つかない生態をしていたりもします。一方、ヒトやマウスは世代交代による高速な進化が難しいため、1個体が記憶によって様々な環境に適応しなければなりません。脳のはたらきは大量のエネルギーや繊細な神経接続のバランスを要求するため、このような記憶形成の過程には栄養供給や調整などの重要なメカニズムが潜んでいるはずです。
大学院では、マウスが恐怖を感じて記憶を形成する一連の過程におけるエネルギー動態を追跡する試みから研究を始めようと計画しています。空腹や貧血が正常な思考を妨げるように、脳におけるエネルギー供給のメカニズムは認知能力に大きな影響を及ぼすはずです。現在は修行の身ですが、いづれは現代人の最大の問いの一つである、思考力や創造性などの「頭の良さ」の正体解明に貢献出来たら幸いです。
2025年05月20日 田島
人智を超えたエナジー田島
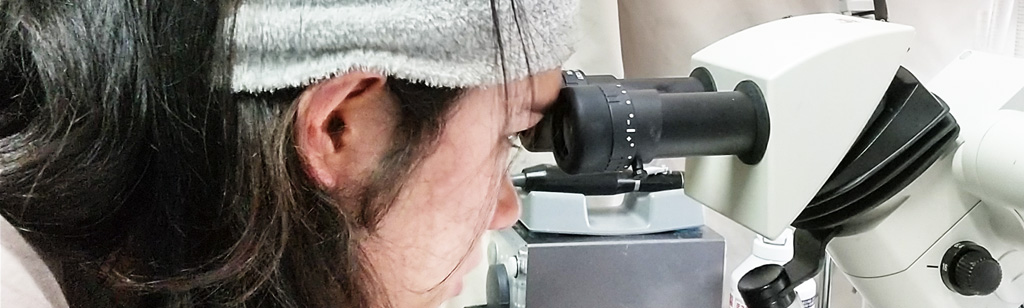
2025年度に超回路脳機能分野の修士課程に入学した田島大智氏、マウスの生体に光ファイバーと電極を留置する手術に挑戦。学習と記憶における脳内エナジーダンスの研究を始めました。
発表論文
〇卒業研究発表のタイトルTAQing 法による線虫 Caenorhabditis elegans の人為的染色体再編成